Last Updated on 2022年3月26日 by 大山賢太郎
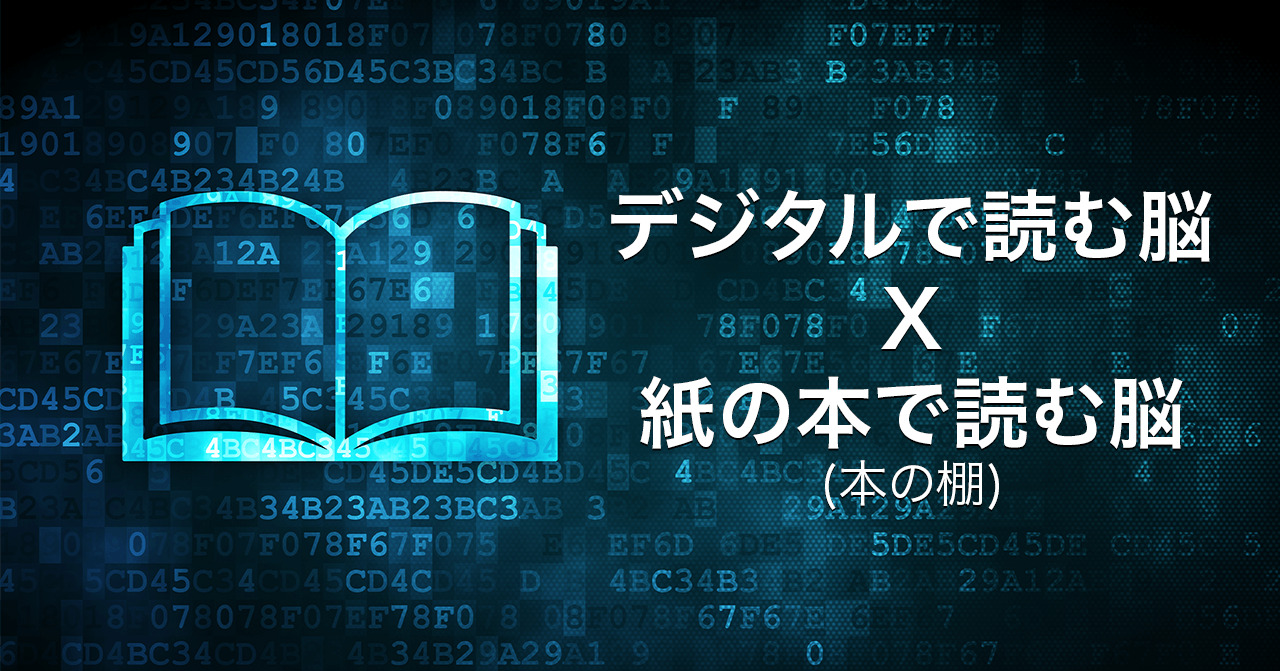
デジタルで読む脳 vs 紙の本で読む脳 – 読書をデジタル画面でするとき、紙の本で読むときとどのように違うのでしょうか?それは、脳に対してどのような影響をおよぼすのか。現在進行中のデジタル化の中で読書と人間の思考がどう変化しようとしているのか、その実態を探ります。
目次
なぜ、デジタルで読む読書と紙の本で読む読書は違うのか?
前回の記事(紙の本と電子書籍: 本当に紙の本で読書する方がよいのか?)では、デジタル本(電子書籍)と紙の本で読書をするとき、どのような違いがあるのかを考えました。そしてデジタル本での読書が増えつつある現在、デジタルであることの可能性にもふれました。
今回は、「デジタルで読む脳 vs 紙の本で読む脳」という観点からみていきます。
デジタルで読む脳 vs 紙の本で読む脳
現在、急速に仕事や身の回りがデジタル化ということばで囲まれるようになってきました。リモートワークはもとより、クラウド化されたサービスからはデジタルの情報が洪水のように押し寄せてきます。
そんな中、重要な情報源は引き続き私たちが大好きな本ですが、他の情報がデジタルとなってきているのに対して、「本は紙の方が良い」という考え方が主流です。
前回は、紙の本とデジタル本について比較しました。そこでは、紙の本とデジタル本の違いについていくつかの点が指摘されました。
- デジタル本より紙の本の方が読みやすい
- 紙の本の方が内容をより良く理解し記憶に残る
紙の本を手にしたとき、ページをめくる時、あるいは本の中の場所を行き来するときの、手触りや視覚の感覚は電子書籍が表示されたスクリーンでは再現できないという点も見逃せません。
また、幼いころから慣れ親しんだ紙の本の読書は、自分の成長そのものであり、読書から得た知識はもちろん、そこからのさまざまな経験や記憶が定着しています。電子書籍という新参者は、その足下にもおよばないという意見もあります。
しかし同時に、インターネットの登場から始まったデジタル化の流れは怒濤のように私たちの読むという習慣を大きく変えてきています。紙で読む方がデジタルの画面で読むよりも優れているという感覚を持ちながら、デジタル情報に圧倒される矛盾を抱えています。
デジタルと紙の情報を読むという、読書の裏側に隠されたストーリーと可能性について探ります。
紙の本の読書とは

脳神経科学者でUCLAのディスクレシア研究所所長のメアリアン・ウルフは“人類は誕生時から字が読めたわけではない”といいます。(「デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳 :「深い読み」ができるバイリテラシー脳を育てる)
人類が文字を読むことを発明したのは、たかだか数千年前のことであり、人間の脳が持つ可塑性と呼ばれる素晴らしい特性によって可能となったのです。
可塑性とは、脳が事故などで障害を受けたときに、それ以外の使われていない脳の神経細胞(ニューロン)がリサイクルされ、もとの機能を再現する働きのことです。これが新しいテクノロジーを受け入れ、これまでなかった能力を手に入れるときにも使われます。
最初の文字は6000年前のシュメール人が使った粘土に刻まれたくさび形文字だったといわれます。これは、商取引や統治のための記録を残すのが主な目的でした。
その後、ヨーロッパでは紀元前500年くらいの古代ギリシャでアルファベットが生まれ、急速に普及していきます。
私たち人間は、生まれてから幼少期に家族環境の中で「話し言葉」を自然に学びます。しかし、文字を書く・読むということは、一定の教育が必要です。
文字の発明後、人間が読むことを学習するために必要な認知能力を発達させるには2,000年の時を要しました。現代の子どもたちは、わずか2,000日でそれを学ばなければなりません。
これにより、はじめて私たちは読書ができるようになったのです。メアリアン・ウルフは、「読むというのはまさに、歴史上最も素晴らしい発明の1つだ」といっています。
しかし、読書は最初から今のように受け入れられませんでした。古代ギリシャでアルファベットが発明され急速に文字が普及し始めたころ、有名な哲学者ソクラテスは文字文化を激しく非難しました。
ソクラテスは口承文化から文字文化へ移行することで失うものが大きすぎると感じていたのです。それは、声の文化特有の対面による口述の柔軟性、高度な記憶術による能力、そして知識が伝わる対象が管理できなくなるといった点でした。
これに対して、ソクラテスの弟子であるプラトンは態度を決めかねていたものの、文字を使って口頭で語られた会話を文字による歴史に残しました。このプラトンが書いた記録によって後世にソクラテスの言葉が残ることになりました。
後に印刷された本も、当初は人の手によって書き写され豪華な装飾がされた書写本よりも劣ると批判されました。それまでの文化人であった16世紀の富裕層は、印刷された本を読みたくないと考えていたようです。
機械で印刷された本は人間味に欠けるというものです。また、手書きの文章の方が脳がより時間をかけて文字を理解しようとするため、読んだ内容が頭の中に定着しやすいというのです。
これは紙の本と電子書籍の比較によく似た議論のように聞こえてきます。
文字が全くなく声の対話でコミュニケーションをしていた口承文化においては、思考は人の記憶にある知識のみに限定されます。また必然的に記憶術が高度に発達します。
ソクラテスは文字にたよることにより、この神聖な記憶が失われてしまう。また声の対話から比較すれば声を記録した文字は死んだ知識であり、顔の見えないものによって悪用されることを恐れたのです。
しかし、文字の文化はプラトンが感じていたとおり、脳を過酷な記憶術や脳にとどめるまでの時間や労力を不要にしました。また脳の記憶をはるかに超える知識を扱うことができ、書くことにより分析的で深い思考が可能となりました。
これはその後のグーテンベルクの印刷技術の進歩で大きな展開を始めます。のちに印刷された本は、段落、章、目次、索引、用語集などが整備され、より読みやすくなっていきます。また、表紙や背表紙、それにページ数が付されることにより完全に規格化され「本という物」の中に固定されます。
この印刷技術は膨大な情報量と正確な知識をいくらでも複製し、流通することができました。著者の考えを時間や場所を超えて直接「視覚」をとおして見ることができるようになったのです。
これにより、外の世界から遮断して紙の本を集中して読む、没頭するという行為が今我々が言うところの紙の本の読書へとつながっていきました。
紙の本の読書は、本質的には直線的です。表紙の扉からはじまり、基本的には第1章から順に進んでいきます。もちろん、目次から他の章へ直接進むこともできますが、基本的な大枠の構成はジャンルの違いはあるもののおおよそシークエンスに従う構成となっています。
2009年の『心理学誌(Psychology of Science)」誌では、読み手は小説を読む脳でなにが起こっているか、脳スキャナーで分析をしました。人間は読書から得た状況を心的にイメージしてシュミレーションし、個人の経験や知識と重ね合わせているということがわかりました。
ニコラス・G・カーやメアリアン・ウルフは、これを『深い読書』と呼んでいます。
では、デジタルで読む脳とは?
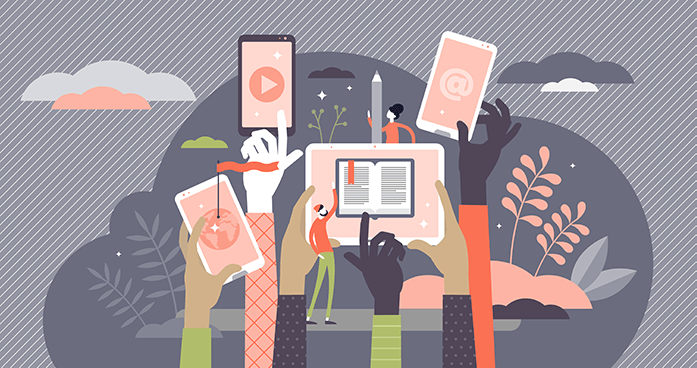
私たちはデジタルの文字文化に完全に囲まれています。それが仕事中のパソコンであれ、プライベート時間のスマホであれ、ひっきりなしにデジタルな情報が飛び込んできます。
このデジタルで文字を読む読書については、近年少なからずの研究が行われています。ノルウェーの研究者アン・マンゲンが行った学生を対象として紙で読むときとデジタルで読むときを比較した調査ではわれわれが感じるところを裏づける結果が出ました。
学生にとっても非常に刺激的な恋愛小説を、キンドルのデジタル画面で読むときと紙の本で読んだときの理解度と読書からの記憶を調べたところ、紙媒体で読んだ方がデジタル画面で呼んだときよりも、ストーリーの筋を時系列で正しく再現できました。また、細部の順序づけがデジタル画面では記憶に残りずらいようです。
2006年のジェイコブ・ニールセンの調査によれば、われわれはWebページを読むとき、本のページのように一行一行直線的に読むことはなく、ローマ字の「F」を描くように視線が動くといいます。
具体的には、冒頭の数行を読んでから、本文の段落を飛ばし読みにしたり、下に進み面白そうな箇所を探して拾い読みする。そして最後まで進むか、面白そうでないと判断すると、リンクや戻るボタンをクリックして別のページへすぐに進んでしまう。この間、わずか数秒での判断が無意識のうちに脳の中で行われます。
「ネットバカ – インターネットが私たちの脳にしていること」でニコラス・G・カーは、デジタル文化を批判しています。カーによればWebページはハイパーリンク、バナー、関連情報など、読む側の注意力を引きつけ注意散漫にすると同時に、理解度も記憶力も浅くなるといいます。
また検索ボックスで文書間のジャンプが簡単にでき、読者の文章への結びつきははるかに希薄で一時的なものとなります。カーはこれを『浅い読書』と呼んでいます。
さらにウルフは、われわれが何十ギガバイトもの情報を毎日継続的に消費するため、無意識に取る行動について、次のように書いています。
まず、簡略化します。次に、できる限り素早く処理します。正確には、短時間で一気にたくさん読みます。そして、優先順位を決めます。知る必要性と、時間を節約する必要性と、こっそり両天秤にかけるのです。
これは読書にも悪影響を及ぼしているといいます。ウルフは脳の可塑性が同時進行し、「にじみ」効果(”bleeding over” effect)が起こり始めているためだといいます。
つまり、WEBの読書になれた脳は、紙の本を読むときにも意識することなく同じような読み方をしようとします。これは、速読や多読など、最近の「より速く・より多く」という読書の傾向とも重なります。
デジタルで読むことにより、これまで私たちが手に入れた読書は「深い読み」を失いつつあり、それはより「浅い読み」へと変化しつつあるのです。これまで脳の可塑性によって掘られた『深い読み』の水路は、新しい水路へと掘り直されつつあるのです。
これに関して注目すべき点は、脳の記憶 – 特に作業記憶(ワーキングメモリ)と呼ばれる短期記憶が変化していることです。われわれの脳は、短期記憶と長期記憶という2種類の記憶でインプットされた情報を保存します。ワーキングメモリとは短期記憶の内で実際に思考や認知に使われる記憶を指します。これが変化しているのです。
ジョージ・ミラーはワーキングメモリの目安として「7プラスマイナス2のルール」を提唱しました。これは最近の研究では、「4プラスマイナス1」になりつつあるといいます。また別の2008年の報告書では、成人の注意が続く長さは5分間あまりで、これはその10年前と比較して約半分になったとのことです。
処理能力を超える情報量が継続的に過重な負荷となると、取り込まれた情報を維持できなくなり、長期記憶との関連付けもできなくなります。学習能力は失われ、理解は浅いものになり、単に取り込まれる情報を消費するだけという機能不全に襲われます。
これは、東京脳神経センター 脳神経外科医 天野惠市氏が呼ぶところの「情報過多シンドローム」の症状に当たります。より多くの情報を調べるほど正解にたどり着けると思い込み、やがて迷宮に迷い込むという悪循環です。(2019 August No.394 戦略経営者: いまどきの健康常識)まるで、猛吹雪の中で起こるホワイトアウトのような現象です。
デジタルで読む脳 vs 紙の本で読む脳: 今起こりつつある移行期とは?

「デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳」でメアリアン・ウルフは、読み書きベースの文化からデジタル文化への移行がギリシャの口承文化から文字の文化への移行と驚くほど似ているといいます。
当時の著名な哲学者のソクラテスは、声の文化に登場した文字による記録は「忘れるための処方箋」だと一刀両断しました。もし人が知識を文字に頼るようになれば、声の文化で素晴らしく発達した記憶力を使わなくなるといいました。
しかし、声の文化にどっぷりとつかったソクラテスには、文字の文化がもたらす大きな可能性を予想することはできませんでした。歴史はそれが間違いだったことを証明しています。
皮肉なことに、ソクラテスの弟子であったプラトンは態度を決めかねていたものの、文字を使って口頭で語られた会話を文字による歴史に残しました。このプラトンが書いた記録によって後世にソクラテスの言葉が残ることになったのです。
声の文化では脳が記憶できる範囲が知識の限界でした。紙の本の文化では、それを本という媒体で大きく拡張しました。そして今それはデジタルとなり、予想もしなかった新しい展開が始まろうとしています。
現在私たちがかかえる問題は、デジタルというまったく新しいテクノロジーに脳が対応し切れていないことです。インプットである情報量が圧倒的に増え、アウトプットとして要求される期待値も大幅に上昇しています。それが情報過多シンドロームの最大の原因です。
一方で紙の本に限界があるのも事実です。口承文化では知識と思考を声と記憶に頼っていました。文字となった知識は印刷技術によって物理的に本の中に閉じ込められ、高度に規格化、構造化されたた媒体として大量に複製されていきました。そしてその後の産業革命や近代化へと突き進むことになります。
紙の本はこれまでも、そしてこの後からも重要な知識の入手方法であることに間違いはありません。
しかしこれは、知識のデータ処理と流通がデジタル化された中で、知識のリサイクル、再利用、処理活用という視点からは、唯一の孤立した存在となっています。なぜならば、紙の本から得た知識を活用しようとすれば、必ず人間のマニュアル操作が必要となるからです。
今、私たちには新しいテクノロジーに対応するアプローチが必要です。われわれの祖先は声の文化から文字の文化へと移行することで歴史を大きく変えました。このまったく新しいテクノロジーを内面化し、デジタルテクノロジーを駆使して紙の本の限界を超えていくときなのです。
読書はどこへ向かっているのか?

ここでデジタルで読む脳と紙の本で読む脳を要約して比較対照してみます。
紙の本で読む脳
良い点:
幼少期から慣れ親しんだ読み方で紙の本を物理的に楽しむことができる。高度に洗練されたストーリーや知識が構造化され、ページをめくりながら直線的に本の著者の思考をたどることができる。場所の感覚や手触りなどを確かめながら、読書に没頭し読み進むことで紙の本の読書独特である空想や想像の時間に浸ることができる。深い読書が可能である。
悪い点:
文字データは紙の本に印刷されるため、直接取り出して記録、要約、処理、アウトプットできない。読書で得られた知識は、必ず視覚から記憶にとどめられるか、視覚からマニュアル操作で手書きのノートやカードに書き写すか、キー入力、画像、音声などを経由してデジタルに変換しなければならない。
デジタルで読む脳
良い点:
縦横無尽に張りめぐらされたハイパーリンク、高度なデータベースとアルゴリズム技術で瞬時に世界中の膨大な情報を得られる。また検索エンジンといったデジタル技術により簡単に大量の知識を収集できる。デジタルのテキストは整理・処理を容易にし、思考を展開し操作することでより高度なアウトプットへ転換できる。
悪い点:
物理的な紙の本で得られる構造や場所の感覚、手触りなど理解や記憶に影響する独特の要素が失われてしまう。大量の情報量に圧倒され、注意散漫となって記憶に残りづらい。浅い読書となってしまう。
デジタル文化はインターネットをはじめとして広く大量の知識を低コストで容易に入手することを可能にしました。しかし、人の脳が処理能力を超えオーバーフローを起こしたときには、自然と理解が浅くなるという傾向があります。
一方で紙の本は、深い読書により理解を高めることができますが、知識を本の外へ取り出して再利用しアウトプットに活用するという点には大きな障害があります。
いま私たちに求められているのは、浅く広くなってしまった読みをより深くする方法です。また同時に、これまでの紙の本を読む脳が抱えてきた知識を処理活用しずらいという問題を解決する、本の知識をすばやく取り出して整理し、アウトプットへとつなげるプロセスが必要です。
デジタルで読む脳と紙の本で読む脳: その未来とは

ウォルター・J. オングはこの分野の古典書となった「声の文化と文字の文化」で、文字を書く技術が発展し、そのあとの印刷技術が登場したかなり後まで声の文化が人の思考の重要な役割を果たしていたといいます。
口承文化から文字が登場したころは、文字は声を記録するだけでした。その後も長い間、声の文化は文字の文化を補完し併存しながら進んでいきます。これは印刷技術によって本が規格化され、誰でもが深い読書にふれるようになった近代になるまで続きました。
この二つの文化にどっぷりと浸かったことにより、紙の本を読む深い読書は生まれました。同様に、デジタル本を読む脳の進化も、紙の本を読む脳と共存することにより同時進行していくことになるでしょう。
メアリアン・ウルフは、「デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳」で次世代を生きる子どもたちには紙の本もデジタル本も両方を読みこなすことのできる「バイリテラシーの脳」を育てる幼児教育を提唱しています。
彼女の提案は、文字の脳が形成される五歳から十歳のあいだに、印刷ベースとデジタルベースの読み方を並行して学ばせるというものです。これは二カ国語を話すバイリンガルの子どもの育て方に似ています。
二カ国語をあやつる幼児は、一つの言語からもう一方の言語に移るときに脳の中で切り替えが起こります。これは、プログラミングなどでも使われるコードスイッチングと呼ばれるものです。幼い脳は学習とトレーニングにより、いずれの体系でも脳が柔軟に対応できるようにできています。これにより、どちらの言語でも深い読みと思考が可能になります。
これは、私たち大人にも共通して言えることです。幼い五歳児ができることが、われわれにもできないはずはありません。私たちはすでに十年以上ものあいだ、何らかの形でデジタル文字に接してきているからです。
紙の本で読む脳のスキルを持ち、さらにデジタルで読む脳の思考回路とテクノロジーを手に入れることができるとすれば、どのようなことが可能になるでしょうか。
この二つのテクノロジーが人の脳の能力と結びついて進化を遂げれば、次のような新しい展開が始まります。
- 必要な情報だけをフィルタ(取捨選択)する
- 後処理が可能なデジタルとして知識を集める
- 収集した知識を可視化し整理して再利用可能にする
- 知識を即戦力として使える
- 整理された知識が記憶に残る
- 新たな発見やアイデアを促す
- 今後のAIなどのテクノロジーを活用できる
これは一体どのようなものか。次回の記事で展開していきたいと思います。
※ この記事を読んでどのようなご感想をお持ちでしょうか。ぜひ、みなさんのご意見を下のコメント欄からお寄せください。今後の展開の参考にさせていただきます。
コメントを残す